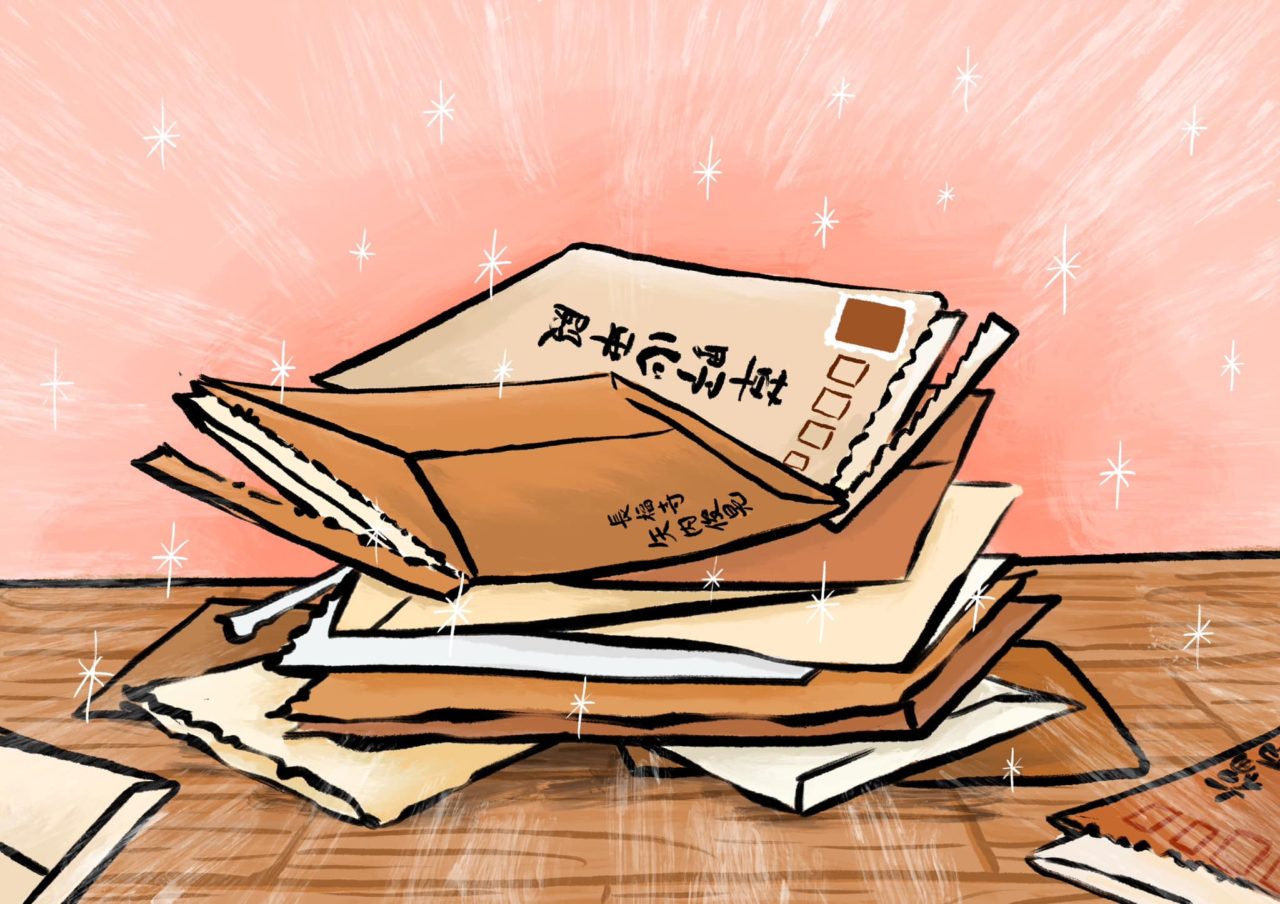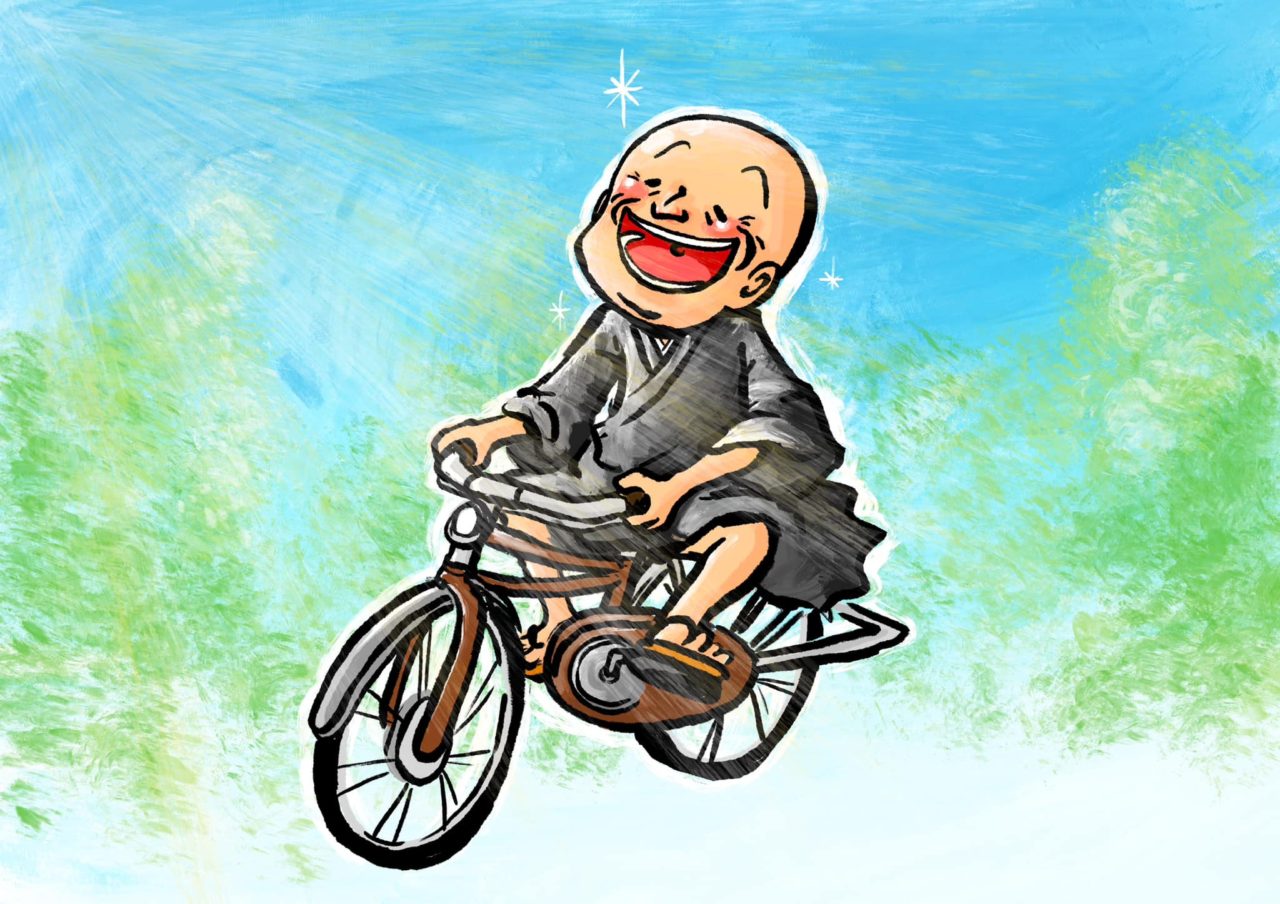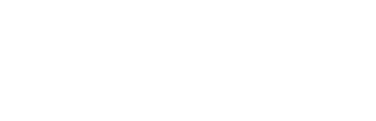モリアオガエルのいる福島県川内村平状沼(へぶすぬま)に惹き寄せられ、お寺の和尚さんからのたくさんのお手紙、ラブコールもらい、やって来た国語の教科書で馴染みの蛙の詩人、草野心平さん。
少年時代、ガギガギザラザラした草野心平さんの心もあたたかく迎え包んた川内村の人達。
この村でありのままに我がままにそのままに更に大きく育った草野心平さん。
亡くなって、45年。
草野心平さんの残した詩と、大好きだったお酒で祀る天山祭り。
やはりここでも、噂の流行り病でここ数年お休みに。
曇り空少し明け、去年からようやく復活。 だけど、お空の曇り空に草野心平さんの家、天山文庫での開演でなく体育館で。 そして顔の下半身隠したまんまの天山祭り。
去年はそこで紙芝居。
今年は。
毎週水曜日の放課後。
画面越しに繋がる川内村の子ども達。
子ども達に、草野心平さんの詩を紙芝居に。
川内村子ども、“紙詩by子“ 育成大作戦。
zoom。画面越し、聞き取りづらい声、聞こえているのか聞こえていないのか届かない声。
まったくちっとも全然言うこと聞かない、思い通りにならない子ども達。
つねってやりたいホッペタにも手が届かない。
最初は思い思いに紙芝居作り。
4コマ紙芝居作りと言ってるのに1コマ紙芝居だったり、20枚描く子どももいたり。
3月。 発表会は学校の子ども達を集めての紙芝居。
せっかくの紙芝居、集まってくれた学校友達に一人残らず見せてやりたいのに、他の子ども達もウロチョロ。 画面越し、もどかしくても何にも出来ない。
自分で描いた紙芝居、それを演ずる子ども。
見ていようがいまいが、お構いなしで一生懸命やっている。
はじめましてのお客さん。有名人でもない紙芝居屋が如何にたくさんの人との距離を縮めるか。 そんな事も教えれたらと思うけど、紙芝居作りだけでいっぱいいっぱい。
だけど、一度会ったきり、画面越し数ヶ月の付き合い。 色んな思い抱えつつも、僕はいつの間にか引き込まれていた。
子ども達の描いた絵、子ども達の真剣な眼差し。 少なくとも僕は子ども達に心つかまれていた。
鳴らす拍子木は何故か、画面越しには聞こえない。
だけど聞こえるパラパラ拍手。
子ども達、皆の紙芝居終え、画面越し、固まっていた肩の力がほっと抜ける。
さぁ、次は7月8日の天山祭りでの紙芝居に向け、草野心平さんの詩を紙芝居に。
僕にはこの詩ってのがよくわからない。
特に草野心平さんのカエルばかり出てくる詩は、わけがわからない。
だけど惹かれる。
“ゆき” “猛烈な天” “道” そして、旧校歌も草野心平さん作詞。
4人の子どもたちが選んだ4つの詩。
水曜日。日が迫るごとに焦る気持ち。 やって来ない宿題。
僕も宿題など期限内にやり遂げた事など一度もないけど、ほんの少し先生側の気持ちもわかった。
大丈夫か? 心配だけど、3月の発表を見て、きっとやってくれる子ども達を知っている。
上手な絵、綺麗な滑舌。そうであったらいいけれど、それにも勝る子ども達の魅力を知っている。
そして、僕よりもきっとずっと、子ども達と多く接している川内村の大人達がお客さん。
だけど、やっぱり心配。
たまりかねて、半年間一緒に向き合って来た、東京のいもうと弟子が一週間前に車で川内村に駆けつける。
画面越しでは伝えきれなかったこともしっかり体温と一緒に届けてくれて、少し安心できた本番一週間前のリハーサル。
いもうと弟子が走ってくれたバトン、僕はもっと頑張らなきゃ。
何一つ手抜きできない。
だから僕はもうしばらく自転車に乗った紙芝居屋で。
本番、前日、大阪から走らせる高速道路を自転車で770キロメートル。
子ども達に自転車に乗せた舞台で紙芝居させてやりたいのだ。 やるのだ。
草野心平さんにたくさんの手紙を送り、招き、たくさんの酒交わし、時間を過ごし、語り合った和尚さん。
川内村を乗り回した自転車は今も寺の門の横、全ての仕事終えひっそりと終わりを待っている。
けど、もう一仕事してもらおうと、和尚さんのお孫さん和尚さんに承諾得て、その自転車で紙芝居を。
ここでまた僕の下手くそ大工。 積んできた廃材にノコギリ当てて、手と足もオマケに切りながら、それを松葉杖に立ち上がった自転車。
乗せる舞台。
これに勝る舞台はない。
子ども達、届かぬ身長はビールケースで。
あとは、翌日晴れて、草野心平さんの家、天山文庫で開演できる事を祈るだけ。
温泉に浸かり、美味しい料理と大して飲めぬお酒を飲んだら、布団につくと気を失うようにバタンと寝てしまう。
翌朝、無情にも雨。
人生そんなに甘くない。
去年に続き、体育館で紙芝居。
出番は最後。
今回は僕が紙芝居するんでない。
なのに、出番近づくと共に高鳴る心臓。
小さな画面。だから見えるようにと、少し傍に寄ってもらい、地べたに座らせるお客さん。
紙芝居。 大人を大人扱いなどしない。 だけど楽ちんパイプ椅子。
鳴らす拍子木。 いっちょ前。
“ゆき”。
「しんしんしんしんしんしんしんしんしん雪降り積もる」
それを繰り返す。
紙芝居の舞台の中の絵の中、雪降る家の中、カエルが笑ってる。
「さぁ、この詩の中で“しん”は何回言ったでしょう?」
そんなの知るかよ。 だけど、子どもの真っ直ぐな瞳、誰も目を反らせない。
答えは32回。 鳴らす拍子木「おしまいおしまい〜」
子どもを包む拍手。
僕の雪がとけるようにホォっとする。
だけど、間をおかず、二番手登場。
何も出来ない。
押さずともビールケース乗り上がり、たくさんに向き合う子ども。
鳴らす拍子木。 拍手。
“猛烈な天”。
草野心平さんの描く猛烈な天は血染めの天。 なんでよりによってこんな詩選んだの?
けど、これにすると、決して譲らぬ子ども。
「わたしの思う猛烈な天は・・・」
サッと引き抜く絵。
「大きな飴が降ってくる!!」
雨でなく飴。 そんな空なんかあってたまるかよ。
「そして・・・」
まだ降ってくる。
「いちご!!」
画面いっぱいに降ってくるイチゴ。
おしまい。
草野心平さんの詩以上にわけわかんないけど、わけわかる。
あの場にいたのかいないのか、草野心平さんにはどう映ったろう?
3人目。
一番騒がしかった女の子は本番になってドキドキ。
そんな感性もあったんだと、少し安心。
小さな声。聞こえぬ声。
だけど逃げ出さず最後まで振り切る。 後ろからただ見守るだけ。
そして向かいにいるお客さん、大人達もしっかり目を逸らさず見てくれている。
草野心平さん作詞、昔の校歌。
「知ってる人は一緒に歌ってください」
だけど誰も知らない。
知ってるかもしれないけど、歌えない。歌わない。
一人絵を抜き語りきる子ども。
胸が熱くなる。
ドキドキ、ワクワク、ハラハラ、ソワソワ。人間が勝手につけた心臓音。 それが聞こえた時はきっと「乗り越えろ」のサイン。
それに立ち向かうから勇気。
今日立ち向かえた勇気。
次はきっともっと出せる大きな声。
道。
最後の女の子。
詩に行き着く前に物語。
この子は前にも20枚描いた。
今回も沢山描いた。
蛇に食べられ親をカエル。
住処無く、見つけた池からも追い出され、そこで思い出した詩。
“わがゆく道よただしくあれ”
“石ころごろごろたりとも我がゆく道よ大きくあれ”。
草野心平さんには申し訳ないが、子ども達の紙芝居詩を通し、僕の胸にも胸に届いた。
最後に今の学校の校歌を合唱。
勇気振り絞りきれぬ大人達の小さな声達より大きな声で歌う子ども。
叩く拍子木。 拍手、笑顔。
一気に力が抜けた。
草野心平さんには届いただろうか?
届いたならどう映っただろうか?
勝手にいじるなと怒ってるだろうか。
知るもんか。
草野心平さんだけでなく、一人一人が主人公。
周りに染められようと、周りに足並み揃えようとしても、どうしようもなくどうしようもない自分。
ありのままに我がまま真っ直ぐに歩いても、きっとぶつかりガギガギザラザラは削れていく。
そうして少しは角が取れて丸くなって行くものなのかもしれないけど、決して失いたくない芯。 自分道。 いつまでも耳澄ませたい心の音。
これから先の子ども達の見上げる空は、もしかしたらたくさんのイチゴが降って来たり、UFOがやって来たり、夏なのに雪がしんしん降ったり、虹がひっくり返り笑うような未だ見た事ない空を見上げることになるのかもだけど、そのまんまを貫いてほしい。
僕だってそうありたい。
草野心平さんを育てた村。
川内村はきっと今も、ありのまんまを育ててくれる村と信じたい。
親、学校の先生だけでなく、こうして紙芝居屋である僕を招いてくれた面白い人がいる。
活かし、活かされることで生きるいのちがある。
人生そんなに甘くもないが、
人生そんなに辛くもない。
水曜日の放課後、言うこと聞かない子ども達の笑顔見れなくなるのを寂しく思う。